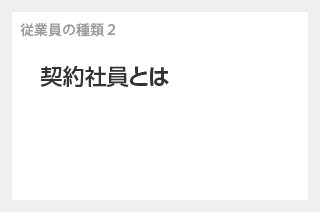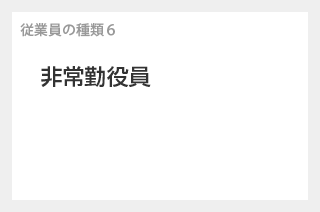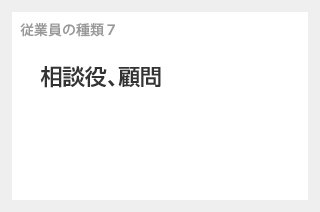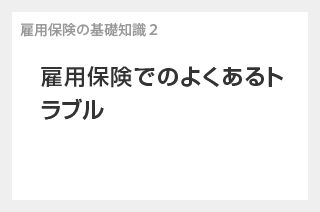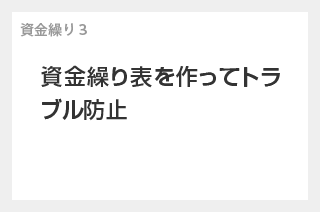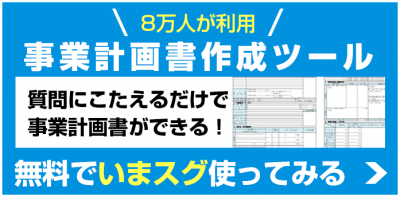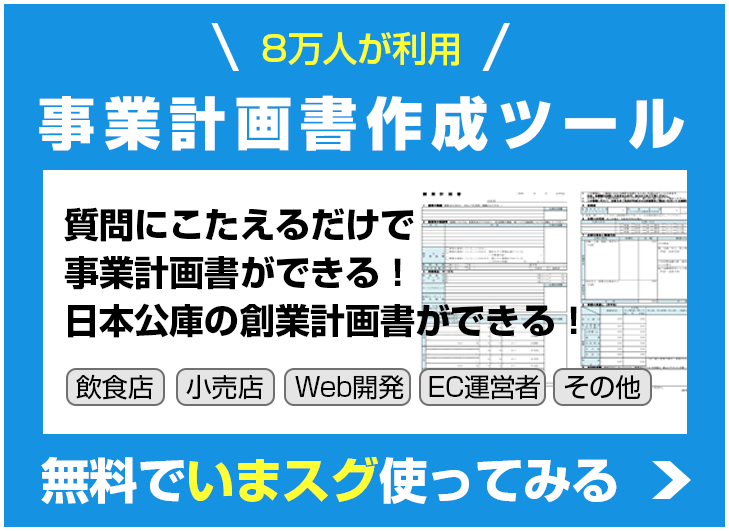会社を設立しても就業規則を作成していない場合や、雇用契約書を交わしていないケースがあります。そういった場合は確実に言った・言わないのトラブルになります。
まず、退職に関するトラブルについて説明します。退職時のトラブルとしては、大きく、
・退職理由のトラブル
・退職申し出と引き継ぎのトラブル
が主に挙げられます。
退職理由のトラブルとしては、失業給付に関わるので問題になりやすいのです。例えば、解雇でなくても会社が辞めろと迫り(退職勧奨)、それに従業員が応じて離職した場合。この場合、退職届を書いてもらったからと言って離職証明書の離職理由を「自己都合による退職」と処理してしまうと、従業員は失業給付を受けるまでに3ヶ月間の給付制限がかかります。しかし、「会社の勧めに応じた退職」となると、給付制限はかからず、すぐにもらえます。ちょっとした違いですが、会社が助成金を利用していると不支給事由にも該当しますので、大きな差になります。同様に、契約期間を定めて雇用した従業員の契約を数回繰り返した場合の雇い止めの問題。これは不当解雇でもよくあるトラブル原因で、平成24年に労働契約法により有期契約労働者の条文も定められました。これとは別に、雇用契約書において、期間の定めのある契約の場合には、契約更新はあるのか、ないのか、どちらか判断できない場合は、何を根拠に判断するかということを明示する必要があるのです。従業員からすると、理由によってはハローワークへ行った際に、「特定理由離職者」とされ、通常12カ月必要な雇用保険加入期間が6カ月で足り、さらに給付制限なく失業給付が出るため、特に興味があるところでしょう。
次に退職の申し出と引き継ぎのトラブルです。単純作業でマニュアル化できるような作業はトラブルにはなりにくいかもしれませんが、一般企業、特に創業したての場合、取引先の状況や業務の進め方、現在の進捗等が従業員の頭の中で進んでいることがあります。辞めたい、働く意思のない奴はすぐにでも辞めてもらって結構、最後の給与は支払わない、という社長もいますが、やはりそこはきちんと引き継ぎをしてもらい、給与を支払わなければなりません。そこで、雇用契約書や就業規則にて「退職の申し出は60日以内」等、企業毎に定めているのです。ただし、民法では2週間前に予告すれば退職できることとなっているので、あくまで任意の規定となります。
また、有給休暇が全く消化されておらず、仮に最大の40日分がたまっていたりすると、通常は5日を超える部分は会社が時季変更権の行使ということで、有給休暇の希望日を変更できるのですが、退職時には変更の余地はありません。そのため、有給休暇を買い取るか(これは退職時のみ有効)、言われたとおりに付与するしかありません。
次に休職の場合です。休職は任意規定で法律上、必ず与えなければならないものではありません。休職は本人の私傷病等により退職の猶予期間という性質があります。
よく前職の就業規則をそのまま運用していたり、親会社の規定の企業名だけ変えて使用している場合があり、とんでもなく厚い保護を与えている場合があります。例えば、「3年勤務した場合には最大5年間の休職期間を与える。その期間は有給とする」といった例です。極端な例ですが、入社1年未満でも休職させる企業もあるでしょう。福利厚生なので、企業毎に決めるしかないのですが、休職期間中も従前の社会保険料の支払いが発生するので、従業員に請求、会社も支払いが必要です。そのため、駆け出し状況での休職制度は「1年勤務で3カ月の休職期間」等と低く設定しておくべきです。
さらに近年では、精神疾患による休職も増加しています。そのような場合に、うつ→回復→統合失調症→回復→うつ等と少しずつ病名の異なる事由での休職を繰り返すパターンも想定されるため、同一事由での休職は通算する規定にし、同一事由も範囲を広く設定しておくべきです。特に精神疾患の場合、従業員が地元の病院で診察してきた場合、主治医は意外と簡単に「うつ状態」等と診断書を出します。しかし、家庭の事情、性格の問題、どのような業務を行っていて、どういう状況になれば復帰できるのかを明確にする必要があります。その為、個人の許可を取って主治医に会社の状況を話してさらに判断を仰ぐ、または産業医(従業員50人以上)とやり取りをしてもらう、もしくは、業務命令として(会社の状況を話した上で)指定する医師や産業医に受診させるといった方法によりできるだけ休職期間を短くするか退職を促す必要があります。
上記は規定がある場合のケースですが、他に規定がなく、創業時からのメンバーだから、等と恩恵的に休職を与える社長もいます。素晴らしいことですが、その際もどの状況で復帰するのか、他の社員への対応はどうするのかを考慮する必要があります。