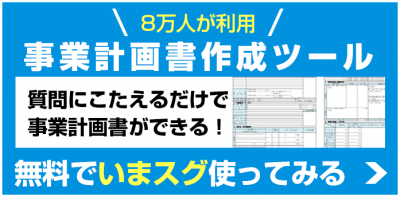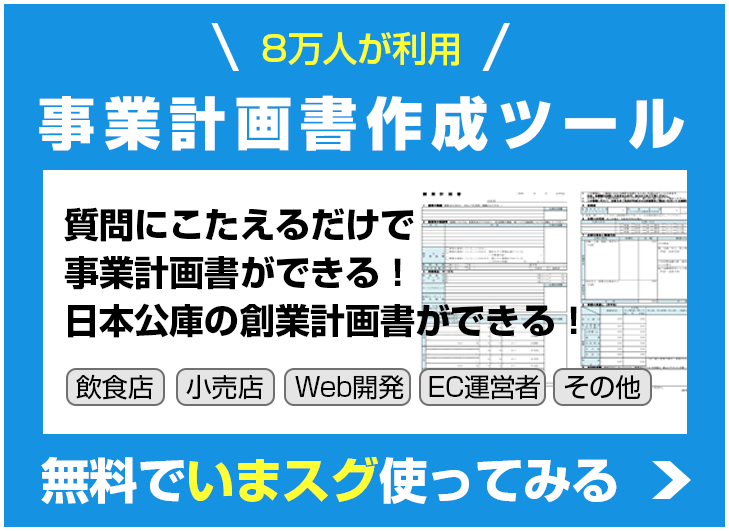- 目次 -
●はじめに
少子高齢社会が到来した現在、改めて中小企業の事業継承問題が大きな課題となっています。戦後、牽引力となり日本経済の先頭に立ってきた中小企業も、経営者の高齢化が進み、世代交代の時期を迎えています。かつて、中小企業の事業継承は親族内継承が主で、経営面と財産面の継承も比較的スムーズに行われてきました。しかし、最近は経営者の親族が事業継承を望まないケースが増え、親族外への継承や第三者への会社売却などが増えてきています。いずれにせよ、事業継承がスムーズに行われないことにより、経営者が育て上げた技術やノウハウが喪失することは、日本経済にとっても大きな損失です。
事業継承を怠ることは、苦労して育て上げた大切な会社が相続トラブルを招くだけでなく、何の関係もない従業員まで巻き込むことになりかねません。そうならないために、今回より3回、親族内継承、親族外継承およびM&Aによる継承のポイント・進め方についてご説明します。
●親族内継承のメリット・デメリット

・社内外からの理解が得られやすい
中小企業の経営者の大半は「できることならば自分の子息に事業を継承してもらいたい」と願うのが実情です。社内の役員や従業員、社外の取引先なども第三者が後継者となるよりは、経営者の子息が後継者であることの方が安心することができ、心情的にも受け入れられやすいです。
・所有と経営の分離を回避することができる
事業継承は「社長の座」という経営面の継承と、「自社株式」という資本面の継承があります。後継者が経営者の子息であれば、経営面の継承を行うと同時に、資本面の継承を行うことにより、中小企業に特徴的にみられる「所有と経営の非分離」の状態を維持することができます。
(デメリット)
・後継者に経営者の資質が備わっているとは限らない
後継者には経営者のDNAが引き継がれているとはいえ、必ずしも経営能力があるとは限りません。そのような状態のまま、後継者として事業継承を行い、仮に、事業継承後に業績が悪化した場合、後継者本人に「自分は後継者の器ではない」や「そもそも後継者になどなりたくなかった」といったマイナスの意識が芽生えてくるようになり、社内・社外といった周囲からも「経営能力がないのに、子息というだけで社長になれた」と思われるようになってしまいます。そうなると、社内のモチベーションも低下し、有能な社員の退社にもつながりかねません。
・後継者候補が複数いる場合、親族同士の対立を招きやすい
経営者の子息が複数いるような場合、親としては「子息全員で協力し、仲良く会社を経営していってもらいたい」と思う気持ちは当然と思われます。しかし、「親の心、子知らず」とはよく言ったもので、例えば、子息全員に役員としてのポストを与え、自社株式も平等に与えたようなケースでは、大半が経営者の死後、経営権を巡って、親族同士で紛争が起こります。
そのような最悪のシナリオを避けるために、誰を後継者とするかを明確に決め、後継者としない親族に対しては財産分与面で手厚く保護するなどの方針を親族会議などで同意を得ておく必要があります。
●親族内継承の進め方

1.経営理念の見直し
経営理念とは、会社経営の基本的なあり方をいいます。「会社の存在意義とは何か」「会社はどこに向かおうとしているのか」を明確にする必要があり、後継者は経営理念をしっかり理解し、継承する必要があります。後継者はとかく、先代との違いをアピールしたがる傾向があります。それはそれで良いことなのですが、「温故知新」という言葉にもありますように、何年も続いてきた経営を継承する以上、その根幹となる経営理念は理解しておく必要があります。その上で経営理念が現状にふさわしくない点があれば一部手直ししていけば良いのです。
2.古参役員との関係
後継者が幼少の頃から会社に出入りしているような場合、長年、経営者の右腕として活躍してきた古参役員(番頭)にとっては、自分の子供のようであり、後継者にとっては親同然、頭の上がらない存在であることが多いのが実情です。後継者が事業を継承した後もそのような関係が続くと、やがて意見が衝突し、対立を招く恐れがあります。そのような対立を避けるために、後継者を補佐してくれる古参役員のみ残し、他の古参役員は経営者と同時に引退してもらうことが望ましいです。
3.社内における教育
同業他社などで数年修業させてから、自分の会社に入社させるケースが見受けられますが、自分の会社に迎え入れる場合であっても、よほどのキャリアがなければ、いきなり役員とすることは避けるべきでしょう。まずは従業員として入社させ、自分の会社の各部門をローテーションで経験させ、経営者に必要な専門知識や現場とのコミュニケーションを習得させることが望ましいです。各部門のローテーションは経営者としての教育という面だけでなく、従業員への「顔見せ」でもあるのです。
◆事業継承でよくあるトラブル。困ったケース。その1
(親族内継承)
地方で小売業を営むA社は、経営者が100%株式を所有する、いわゆるオーナー企業でした。経営者には長男、次男、三男と3人の子息がおり、長男が実質的な後継者として会社の経営に携わってきました。経営者は長男を後継者にすることについて次男と三男をはじめ、親族からも了承を得ていました。しかし、「いずれは兄弟3人で仲良く経営を続けてほしい」という経営者の希望もあってか、実際には経営に関与していない次男と三男も取締役として名を連ね、役員給与を得ていました。そんな中、相続が発生しました。遺言書は作成していませんでしたが、親族内では長男が後継者であることから、自社株式も長男がすべて相続するものと思っていました。しかし、ここにきて次男と三男が「自分たちは取締役なのだから、自分たちも株式を取得する権利がある」と言い出したのです。兄弟3人で株式を等分すると、実質的な後継者である長男単独では普通決議も通すことができません。そうなると、会社の経営が不安定なものになってしまうため、何度も親族会議を開き、ようやく次男と三男を説得し、株式以外の財産を次男と三男に相続させることで決着しました。生前に口頭の了承を得ていても、遺言書がなければ、相続発生後にこのようなトラブルが発生することは、よくあることです。