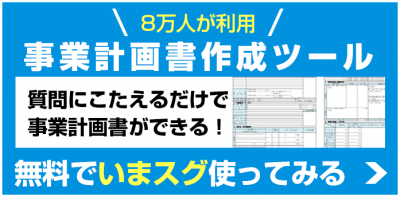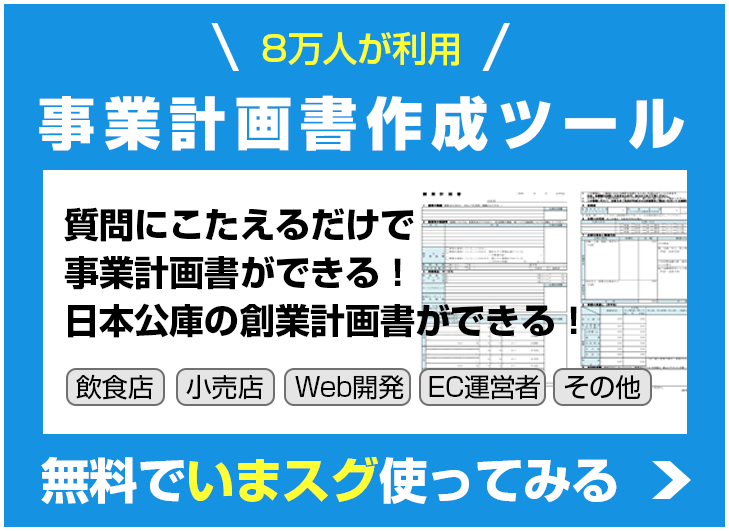- 目次 -
第137回
英治出版株式会社/
代表取締役
原田英治 Eiji Harada
1966年、埼玉県生まれ。埼玉県立大宮高校時代、AFS(公益財団法人AFS日本協会)の制度を活用し、1年間アメリカ留学を経験。1991年3月、慶應義塾大学法学部法律学科を卒業後、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に入社。1995年2月、同社を退職し、約4年間、家業である印刷会社での勤務を経て、現在の英治出版株式会社の前身となる有限会社原田英治事務所を設立。代表取締役に就任。妻と二人、埼玉の自宅を事務所とし事業をスタート。2000年6月、株式会社に改組し、代表取締役に就任。後の「仕事術本」ブームの先駆けとなった、『マッキンゼー式 世界最強の仕事術』がベストセラーに。また、「ブックファンド」という新しい出版ビジネスモデルを考案し、著者の夢を応援するインフラを整えた。2003年6月、韓国Book21と業務提携。翌年、日韓初の合弁出版社Eiji21 Inc.設立。2006年、Eiji21 Inc.を完全子会社化。同社の主な出版物としては『女子大生会計士の事件簿シリーズ』『ウォートン経営戦略シリーズ』『社会を変えるを仕事にする』『イシューからはじめよ』『学習する組織』などがある。
ライフスタイル
趣味
子どもと遊ぶことです。
13歳の長男と、3歳の二男の父親です。長男は柔道を始めて、なかなか遊べなくなりましたが、二男とは休日に自転車の練習をしたり、おもちゃで遊んだり。子どもと遊ぶ時間が一番の息抜きです。あとは、囲碁くらいですかね。
好きな食べ物
和食です。
好き嫌いはあまりなく、何でも美味しくいただきます。中でも好きなものを挙げろと言われたら、寿司、うなぎなどの和食でしょうか。お酒は普通にたしなみます。よく飲むのはビール。ワインも好きです。
行ってみたい場所
アフリカ大陸です
BOP(Base of the Pyramid)ビジネスマーケットの視察で、アフリカのルワンダを訪れました。それ以来、アフリカに興味がわきまして。人類発祥の地といわれるエチオピア、マラウィー湖のあるマラウィー共和国にも行ってみたいと思っています。
お勧めの本
『起業家の本質』(英治出版)
著者 ウィルソン・ハーレル
アメリカの有力ビジネス誌『Inc.』の元発行人で、「アントレ・プレナー・オブ・ザ・イヤー」の受賞者でもあるウィルソン・ハーレルが、急成長企業をつくり出す「起業家の本質」に迫っています。私がこの本から学んだ、一つの真理をご紹介しておきます。起業家はリスクを冒さない。起業家はリスクがリスクでなくなるまで、事業に想像力を加え続ける。そして、最終的に事業をやらない自由を持っている。
関わるすべての人の「夢」を大きく育てる出版社。
共感と応援をコンセプトとし、著者の夢をパブリックに!
「出版=版を出す」ではなく、「パブリック(公)にする」こと。人や物語や知識・情報をパブリックにするのがパブリッシャーの役割。2002年、英治出版は「パブリッシャー宣言」を世の中に向けて発信した。以来、「ブックファンド」の手法など、著者の夢を背伸びさせる応援ビジネスで、一般の出版社とは一線を画したユニークな事業展開を続けている。そんな異色の出版社を創業したのが、同社の代表を務める原田英治氏である。「会社の規模など数値的な目標よりも、英治出版がいかにパートナーの力を引き出しながら、社会の中でより有効に機能していくか。いかに大きなソーシャルインパクトを残していくか。それが自分たちの評価尺度としては合っている気がしています」。今回はそんな原田氏に、青春時代からこれまでに至る経緯、大切にしている考え方、そしてプライベートまで大いに語っていただいた。
<原田英治をつくったルーツ1>
父の口癖は「起業して家業を乗っ取れ!」。
幼稚園の卒園式で書いた将来の夢は「社長」
私が生まれたのは、埼玉県の浦和です。家業は祖父が起業した印刷会社です。父の代に出版や食品事業に進出し、弟は今、シェフ兼食品会社の社長になってベルギー料理店を経営しています。そして私は自分で起業しましたから、「社長!」と呼ばれたら、家族3人が「はい?」と振り向く(笑)。言ってみれば、経営者一族ですね。会社は都内にありましたが、父が自宅に持ち帰った仕事を社員の人たちと一緒に手伝ったり、倉庫の流れ作業もしたりした記憶があります。そうやって、父はよく仕事場に私を連れて行ってくれました。お中元やお歳暮を配る際の得意先回りについて行ったことも。そんな父の口癖は、「親の会社を継ぐのは大変だ。どうせなら、自分で会社をつくって、この会社を乗っ取れるくらいになれ」。幼稚園の卒園式で書いた将来の夢は、「大人になったら会社の社長になる」でした。うまく刷り込みされていたんだと思います。
3歳の頃から水泳を始めました。理由は、親が泳げなかったから。自分たちができなかったことをやらせてくれたんですね。週に6回はスイミングスクールに通って、その隙間をぬって、塾にも行っていました。市内の水泳大会では、だいたい1番を取っていましたが、練習があまりにしんどくて、小学5年でいったん水泳は卒業。才能が開花する前に、やめてしまったという感じでしょうか(笑)。あとは、祖父と父が好きだった、囲碁を小学4年から習い始めています。囲碁は自然と算数の素養も身につけられるんです。私の子どもは小学校に上がる前から、囲碁を始めましたが、早い段階で足し算、引き算、簡単な掛け算などもできるようになっていましたね。百ます計算がいいとか言われているようですが、小さな頃から囲碁も算数を覚えるいいツールになると思うんですよ。今でも時々、グロービスの堀義人さんらが通う囲碁サロンで碁盤を囲んでいます。
小学生の頃、父に「おまえはアイデアマンだ」とよく言われていました。父が帰宅した際、いろんな話をしている時にたびたび。そんな刷り込みもあって、アイデアを考えることがとても好きでした。当時、こんな“なぞなぞ”があったんですよ。「光より速いものはなんでしょう?」。答えは、人間の「想像力」でした。それ以来、想像力という言葉に敏感になりましたね。講演に呼ばれると、たまにこのなぞなぞの話をするのですが、ある大学生の答が「のぞみ」だったんですよ(笑)。そう、新幹線ですね。笑っちゃいましたけど、「こだま」より早いのが「ひかり」、それよりも速いのが「のぞみ」。「望み」って、言い換えれば、人間の想像力から生まれる賜ですよね。そういった意味で、実は新幹線のネーミングって意外と考えられているなあと。
<原田英治をつくったルーツ2>
徒手空拳で動き出した公民館でのライブ計画。
その実現が自分にとって大きな自信となった
中学に進むと、水泳を再開するために、水泳部に入部しています。私たちの頃って、中学がかなり荒れていた時代で、ケンカはけっこうやりましたね。この頃からすでに、身長は今と同じ175センチくらいあって、水泳で鍛えた腕力も。ちょっとした不良気取りで、普通のやつには負けない自信がありました。で、中学2年くらいから、ギターにはまりました。気の合う友人たちとバンドを組んで、ビートルズやオフコースのコピーを練習するわけです。最初はフォークギターからでしたけど、だんだんとエレキギターも使うようになって。文化祭や予餞会なんかのステージに出て、何度かライブをやりました。これがすごく楽しかったんですよ。
私は県立大宮高校に進学したのですが、ほか4人のバンド仲間は、みんな別々の高校へ。でも、入学したて、1年の5月頃、「また一緒に何かやりたいよね」という話になって、「じゃあ、ライブやろう」と。普通なら「街のライブハウスで」という発想が浮かぶのかもしれませんが、私が目を付けたのは浦和市民会館。普通にプロのミュージシャンがコンサートで使うような会場です。役所の担当者に「会場をお借りしたいのですが」「誰が?」「僕たちです」「君ら中学生だろ」「いえ、もう高校生です」と(笑)。そうしたら、まずは「親の許可を取ってきなさい」、その後は「校長先生の推薦状を」。親はすぐにOKしてくれましたが、私を含め5人の高校の校長先生の推薦状がね。高校に入ったばかりの新入生が校長室に行ってお願いするわけです。もちろん、いきなり職員会議の議題となりました。
会場使用の許可が出て以降、スタジオで一生懸命練習しました。ただ、潤沢な資金があるわけではないので、ライブ当日にスタジオのチラシを配ることを条件に、スタジオレンタル料をディスカウントしてもらったりと、いろんな工夫をしながら。そして結果、7月にライブを実施できたのです。ライブが行われた日の天候は生憎の台風でしたが、200人以上の観客が集まってくれました。演奏のデキですか? まあ、それは置いておいてください(笑)。ただ、誰もが最初は無理だろうと思った取り組みでしたが、自分たちの力で何とか成し遂げることができた。動き出せば、何かが始まって、変化が起こり、かたちになる可能性が生まれるんです。このライブを実現したことは、本当に得難い経験になりましたし、自分にとってとても大きな自信になりました。
<米国留学>
1年間、留学生として海外に身を置いた経験。
異文化の間の差異がビジネスヒントとなる
高校時代の生活を振り返ってみると、水泳部の活動と、囲碁ですね。囲碁は、高2の時、団体と個人戦で埼玉の県代表になって、全国大会に出場しています。どんな競技であっても、全国大会に出られる人って希少じゃないですか。結果、全国本選では3回戦で敗退しましたが、これもいい思い出です。AFSという、ホームステイでの10代の高校留学を中心に、国際教育や異文化交流を行う留学団体があります。私のいとこがこの制度を使って数年前に留学していたんですよ。彼からいろんな話を聞くうちに、自分も留学したいと思うようになりまして。高校2年の時に試験を受けて合格し、3年を休学して1年間、カリフォルニアのサンタバーバラにある現地の高校に留学することに。同年代のホストブラザーがいる家にホームステイさせてもらい、1年間のアメリカ生活が始まりました。
1年間でその高校の卒業資格を得ようと、学年カウンセラーと相談したら、かなりの勉強量が必要なことが発覚。勉強は必死でやりましたよ。ただ、同年代のホストブラザーがいたので、何をするにも彼に頼っていればOK。そのせいで、あまり英語を使わなくてよくなって。日本にいた頃は冗談ばかり言っていた私が、寡黙な男に変身です(笑)。アメリカの高校生の中には、すでに車を乗り回している人が多く、彼らは車を維持するために、いろんなバイトをしているんですね。そんな少し大人びた彼らから、たくさんの刺激をもらいました。アメリカで暮らす中、いろんなギャップの存在を知りました。大きなゴキブリが出るんですが、「ゴキブリホイホイ」が売ってない。ハンバーガーのひき肉につなぎを使っていないから食べづらいし、美味くない。だから、コーラを1リットルも飲むんだな、とか。アメリカ人に、日本のハンバーグを食べさせたら、びっくりするだろうな、とか。異文化の間に存在する差異はビジネスにつながる。そんなことをよく考えていました。
できることなら若いうちに一定期間、海外に身を置く経験はしておいたほうがいいと思います。ただ、昨今、AFSの留学希望者が減っているそうです。グローバル化がこれだけ叫ばれている時代なのに、すごくもったいないですよね。無事に1年間の留学期間を終えた私は、翌年の7月から再び大宮高校の3年に復学します。ここから現役で大学合格を目指すのは難しいと判断し、1浪覚悟で受験準備を進めました。もちろん、いつか自分で会社をつくるという思いは変わりません。「通訳は雇うもの、弁護士も雇うもの」という父からの教えもあって、経営者として、雇った人の言動が正しいかどうか判断できるリテラシーくらいは大学時代に身につけておこうと考えました。アイデアマンとして可能性のある事業計画を実行したとして、人に騙されない程度の勉強はしておきたかった。そんな理由で、法学部を志望し、慶應義塾大学に進学。ちなみに、大学入学後は、言うほど勉強はやっていません(笑)。
<コンサルティング会社へ>
プロジェクトマネジメントの要点を体で覚え、
5年後に家業の印刷会社へ取締役として転職
一番力を入れたのは、AFSのボランティア活動です。高校時代、大学生のボランティアスタッフの方々が、とてもかっこよく見えたのです。また、留学という貴重な経験をさせてくれた団体に恩返しがしたいという思いもありました。主には、副代表として、日本の高校生と留学生の交流キャンプの仕切りを担当しました。日本の大学生200人を公募し、参加留学生は50人、ボランティアスタッフ50人と、300人規模で行う一大行事です。そのために要する予算は数百万円。そして、4泊5日の交流キャンプのために、1年がかりで周到な準備を行い、事故なく楽しい異文化交流イベントを敢行することがミッションです。また、派遣部にも所属し、大学3年の時には派遣部長としてメイン会場となった代々木のオリンピックセンターに、年間50日以上は寝泊まりしていたんじゃないでしょうか。その活動を3年まで続けて、4年になり、就職活動の時期が訪れます。当初は就職せず、卒業後すぐに起業しようと考えていたのです。
そのために、仲間を集めて、毎週事業アイデアを考えるミーティングを続けていました。しかし、自分で考えるビジネスは、学習塾とかイベント事業とか、斬新なものがなかなか出てこない。2年先に社会人になった高校時代の同級生たちのアイデアも、いまいち。結局、経験がないものには想像力が働きづらいことがわかりました。また、今は神輿をかつぐタイミングではないということも。そこで、計画を変更し、将来の起業のために役立つ経験が積める会社にいったん就職することに。そして、さまざまな事業会社に仕事で携われ、会計とシステムにも強いコンサルティング会社、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)にお世話になることを決めました。給料もけっこうよかったですし(笑)。
入社して最初のプロジェクトが、ソフトウェア開発でシカゴでの仕事。世界中のスタッフが400名くらい集結する大プロジェクトで、日本からは私を含め、4人が送りこまれました。4人でチームを組むのかと思っていたら、全員バラバラ。新入社員の私としては陸が見えない大海原に放り込まれたようなものです。結果、私は4カ月でこのプロジェクトを離れ、日本に戻されることになります。理由は、スケジュール超過によるオーバーバジェット。たかが数時間の無駄でも、見逃してはくれないのです。悔しさを感じるとともに、世界的なコンサル会社のプロジェクトマネジメントの時間と成果に対する意識の高さに驚かされました。帰国後、さまざまな大手企業のシステム関連プロジェクトに携わる中で、数十億円の仕事という規模感と責任感、計画と結果といった仕事観を体験することができました。そして、5年目に入る前、私はアンダーセンを退職し、家業の印刷会社に取締役として転職することになるのです。
●次週、「新しいかたちの出版ビジネスを確立。共感がキーワード!」の後編へ続く→
誰かの夢を応援すると自分の夢が前進する――。
共感資本主義の世の中の到来に貢献し続けたい
<起業>
スタート当初はまったく本が売れず苦労の連続。
電車賃を浮かせるためマウンテンバイクで東京へ
「サラリーマンを5年やったら辞められなくなる」。父から何度か言われていたんです。将来の起業の夢は具体的にやりたいビジネスがあったわけではなく、父の会社を乗っ取るくらいの実力をつけることが大前提です。父が体調を崩し、叔父に社長の座を譲ったタイミングでもありました。そんな父からの誘いに、小さな組織で取締役というポジションで、組織マネジメントに参画できることは十分に魅力的な仕事だと直感。そして、組織を成功に導く一つのプロジェクトとしてとらえ、コンサルタント視点で経営に取り組むことにしたのです。そうやって中小企業に身を置いてみると、おかしなポイントがたくさん見えてきました。後継者候補とはいえ、若い私に追い風ばかりではありませんでしたが、業務フローの整理などいろいろな提案を行いました。しかし、経営との温度差を徐々に感じるようになって……。関わっている人たちの夢が大きくなる場所とは思えなくなってしまったんですよ。
入社して4年後の1999年、会社を去る決心をしました。関連出版社でビジネス系書籍の翻訳版権をいくつか取得していたのですが、経営は「出版の意思はない」と。せっかく信頼いただいて権利を提供してくれた著者の方々に申し訳ないじゃないですか。だったら「自分がその版権を買い取ります」と。そして、妻と二人で埼玉の自宅の一室をオフィスとし、出版会社を創業したというわけです。今も変わっていませんが、私たちの会社と仕事をすることで、社員、著作権者、取引先など、すべてのステークホルダーの夢が大きくなっていく組織をつくりたいというのが創業当時からの理念です。が、スタート当初はまったく本が売れず、苦労の連続でした。打ち合わせの際は、電車賃を浮かせるために埼玉からマウンテンバイクで東京に行っていました。「自転車が趣味なんですね」と聞かれたら「そうなんです」と。だって、著者の方々もお金のない出版社と組むのは不安でしょう(笑)。打ち合わせの場所も、千円以内でお釣りがくるスターバックスなどでしたよ。やっと一息つけるようになったのは、『マッキンゼー式 世界最強の仕事術』がベストセラーになった2001年からでしょうか。
その前年に、組織を株式会社化し、2002年、都内にオフィスを移転しました。また、初の社員を採用したのもこのタイミング。雇用者となった責任感をひしひしと感じ始めましたね。それで自分たちの役割である出版を再定義してみようと思ったんです。自分たちの役割は出版社というよりも、「パブリッシャー(publisher)」だと思っています。パブリッシャーの語源はパブリック(public)であり、私たちが共感し、応援したい著者や作品をパブリックにすることで、著者の夢や目標を前進させる「応援ビジネス」。これが私たちのミッションです。もうひとつ、英治出版が一般の出版社と異なる特徴は、ブックファンド事業でしょう。出版資金を外部調達することから「ブックファンド」と呼んでいます。個人や企業など出版業を本業で営む人でなくても、プロジェクトとして1タイトルからの出版事業に挑戦できますし、出版社としてもリーズナブルにタイトル数を増やせます。もともとは著者の方を応援し、出版を通じて夢を前進させたり、背伸びさせてあげる仕組みだと考えていましたが、現在では外資系コンサルティング会社など、企業ブランディングの出版に使われることも多くなりました。
<ブックファンドの効果>
ベストセラーにはあまりこだわらない。
著者の“背伸び”を応援していきたい
『さおだけ屋はなぜつぶれないのか?』で一躍有名になった、公認会計士の山田真哉さんは、ブックファンドをうまく利用した人ですね。当社から出版した『女子大生会計士の事件簿』シリーズは現在第6弾まで刊行され、20万部のベストセラーです。他の出版社から出ている文庫版などを合わせるとシリーズで100万部を超えているようです。そもそも『女子大生~』の企画は、まだ会計士補だった山田さんが、ほかの出版社に持ち込んでボツになっていた企画でした。それを当社で発行するに当たって、ご本人の全額出資でファンドを組成したのです。そして、先ほど説明したように大ヒット。ちなみに、一般的に書籍を出版した場合、著作者への印税は10%が普通と言われています。しかし、ブックファンドを活用した結果、山田さんに戻ってくる配当分が非常に大きくて、印税に換算すると30数%に。そして、彼はブックファンドで得た配当を原資に、当社と広告戦略を展開したことで作家としてブレイク。その後、光文社さんから声がかかり、『さおだけ屋~』の大ブレイクにつながったというわけです。
誰かの夢を応援すると自分の夢が前進する――。Give and Takeではなくて、巡り巡って自分が後押しされている気がするんです。たとえば、英治出版の資本金は今現在、8922万円になっていますけど、アクセンチュア時代の人がけっこう応援してくれているのです。しかも、コンサルタントなのに決算書を見ずに投資してくれている。やはり、数字ではなくて共感なんでしょうね。また、インプレスの創業者である塚本慶一郎さんも、ある時食事にお誘いして、「すいませんけど、2000万円、貸してくれませんか」とお願いしたら、「ああ、わかったわかった」と。2、3回しかお会いしたことなかったんですけど、この時も決算書なんかお見せせずに(笑)。これらの方々の応援がなかったら、韓国の「Eiji21」を完全子会社して今のような展開はできなかったでしょう。あと、当社として、これまでブックファンドの約70タイトルを含む、約190タイトルの出版も難しかったと思います。
ベストセラーを実現したいか? それほど部数にはこだわっていないんです。ただし、著者がやりたいことを、少しでも背伸びさせて実現してあげたい。そこには常にこだわっています。著者の夢を応援していくのが英治出版の仕事だと考えているので。もちろん、当社が関わるプロジェクトの一つ一つに決めた目標はありますし、それをクリアしていくことによって著者にいい効果があればいいなとは思います。ブックファンドの場合、本はそれほど売れていないけど、本をきっかけに営業効率が上がった、引き合いが増えたという成果があれば、それはそれで私たちが応援した意味があったということですからね。
<未来へ~英治出版が目指すもの>
社会の中でより有効に機能していくか。
いかに大きなソーシャルインパクトを残せるか。
繰り返しになりますが、誰かの夢を応援することで自分の夢が前進する。これをベースに経営を続けていきたい。今、主に出版しているジャンルが、ソーシャルイノベーション、社会起業とか。そういった社会問題に特化したものと、途上国の経済開発であるBOP(Base of the Pyramid)に関係した新しい経済分野。あとはリーダーシップ、システム思考とか、ダイアローグといわれる、社会が支配的な文化から対話的な文化へ変わっていくうえで必要な、相手の力を引き出すようなパートナーシップの世界へ移行していくための組織学習分野。これら3つが英治出版の大きな柱になっています。この3分野を融合させていくことによって、今日よりも明日がよりよい社会になることに貢献していきたいのです。そして、今だけでビジネスをするのではなく、「絶版にしない」というコンセプトを持って、未来の読者にも役立つ仕事を続けていく出版社でありたいと思っています。
では、出版だけで終わるかといったらそうではなくて、僕らのネットワークでいろんな社会問題解決を支援できることが増えている気がしています。それこそ、BOPという言葉を生みだしたスチュワート・ハート教授、CKプラハラード教授の著書も当社で翻訳しているわけです。そのほかにも、ブルー・セーターなど途上国の開発のためのNPOベンチャーキャピタル・アキュメンファンドもそう。当社が直接コミュニケーションし、BOPビジネスを本気で目指す方々を、彼らやケースに取り上げられた企業や社会起業家とダイレクトにつなげることができる。そういったさまざまなチャンスを今後提供していけるかもしれないので、それが自分たちの新しいビジネスになっていけばいいし、自分たちの理念や思想の範囲であれば、誰かを応援しながらそれが新しい領域へと広がっていけばいいと思っています。
もちろん、単年度の数字の目標は立てますが、会社の規模など数値的な目標はあまり置きたくないのです。もう、量の時代ではないですし。それよりも、英治出版がいかにパートナーの力を引き出しながら、社会の中でより有効に機能していくか。いかに大きなソーシャルインパクトを残していくか。それが自分たちの評価尺度としては合っている気がしています。また、いろんな言語を扱っていきたい。今は韓国だけですが、将来的にはやはり英語圏でも挑戦したい。ちなみに、サンクチュアリ出版創業者である高橋歩さんの書籍は、ブックファンドの仕組みを活用することで、サンクチュアリ出版が韓国での出版を成功させています。印税だけでは足りない、本格的に進出すれば多額の資本投下と事業継続の責任が生まれる。そのギャップを埋めるために、ブックファンドをうまく活用してもらっているのです。創業当初は「紙の出版社を世界に」と思っていましたが、今ではiPadやKindleなど電子メディアも出てきましたので、、紙のメディアに執着しすぎずに、英語圏や英語圏以外の言語でも世の中に流通させながら、世界に新しい対話を生み出していきたい。開発途上国ほど、出版のチャンスの伸びしろは大きい。必ず、英治出版の応援が生かされると思っています。
<これから起業を目指す人たちへのメッセージ>
利益が大きいことだけが存続の意義にはならない。
共感資本主義の世界がだんだんと近づいている
「シックス・ディグリーズ・オブ・セパレーション」。6人の友達を介せば、世界中の誰とでもつながることができるという法則。私は、これが好きなんですよ。でも、6人は大変だから、「スリー・ディグリーズ」を使える人になろうと思っています。この話を知ってから、パーティなどで名刺交換しなくなりました。当然ですが、「ワン・ディグリー」づくりを生涯かけてやったって、全人類とは知り合えませんよね。ということは階層の深い人と知り合いになるほうが、世界は早く狭くなるわけです。そうするためには、目の前の人を大事にするしかないんですよ。友だちに友だちを紹介してもらう場合、まず自分の友だちと仲良くしておかないとしょうがない。その絆の深さが、次の階層を呼んでくれるのです。ある時、知人から「ヤフーの創業者であるジェリー・ヤンのメールアドレスを教えて」と言われたんです。僕はまったく知らなかったので、知り合い数人にメールで聞いてみたら、何と2人から「彼のアドレスはこれ」って返信されてきた。びっくりしましたね。
それでわかったことがあります。私にとってジェリー・ヤンは「ツー・ディグリーズ」だったということです。その発見があってから、あれ待てよ、ビル・ゲイツもリチャード・ブランソンも「ツー・ディグリーズ」じゃないか。世界のビジネス界のVIPが意外と近くにいるということがわかった。講演でよく話すんですが、「皆さん、今日、私とワン・ディグリーになったということは、ビル・ゲイツもリチャード・ブランソンもみなさんのスリー・ディグリーズということですよ」。なので、一度自分の「スリー・ディグリーズ」までに、どんな人がいるのか想像してもらいたいんです。そして、改めてお互いの「スリー・ディグリーズ」を想像しながら対話すると、そうとう面白いことができると思うのです。しかし、まずは目の前にいる人を応援しようと思うことから絆づくりのすべてが始まるのです。
「共感資本主義」という言葉を時々使いますが、それが資本主義経済の原点だと思っています。たとえば、大航海時代に、冒険家の夢を資本家が応援して、そこから生まれた貿易などの利益を分配していた。誰かの夢を応援したら利益が返ってきたということです。が、それがいつからか、利益が大きなほうが社会に貢献しているとなった。でも、それは本当でしょうか。世の中には、お金でお金を生む、コールドマネーというお金が増えてしまいました。でも、私はシンプルに夢に投資したリスクの分だけリターンが得られる、ウォームマネーのほうが好きなのです。そこに共感してくれる人が増えていけば、支配やコントロールが幅を利かせる社会ではなく、相手の力をお互いが引きだす共鳴社会が生まれるのです。これからは、利益が大きいことだけが存続の意義にはならないと思います。誰かがあるビジネスに共感し続けてくれるからこそ、会社が生き残っていく。そんな共感資本主義の世界がだんだんと近づいていることに、気づいてほしいと思います。
<了>
取材・文:菊池徳行(アメイジングニッポン)
撮影:内海明啓