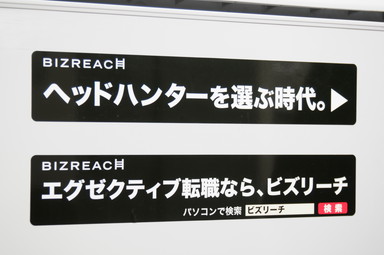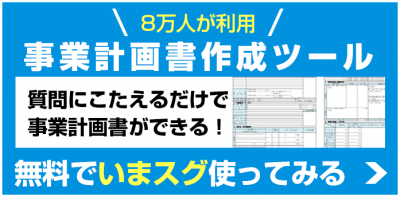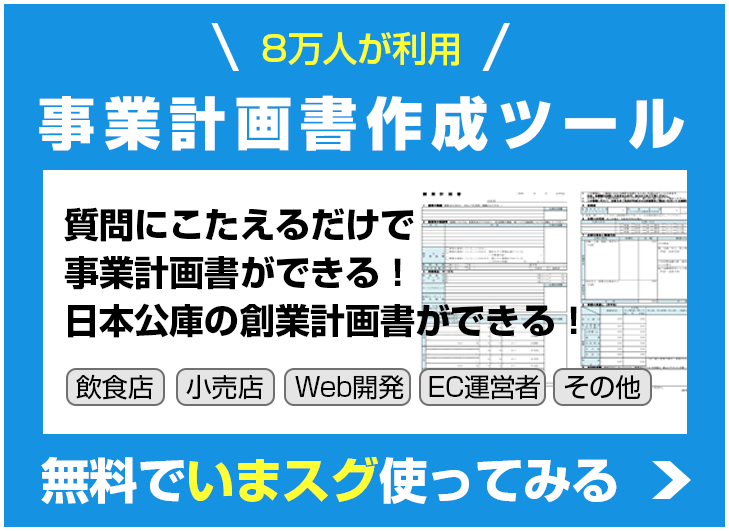- 目次 -
第120回
株式会社ビズリーチ 代表取締役兼CEO
南 壮一郎 Soichiro Minami
1976年生まれ。1999年、米・タフツ大学数量経済学部・国際関係学部の両学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券に入社。東京支店の投資銀行部においてM&Aアドバイザリー業務に従事する。その後、香港・PCCWグループの日本支社の立ち上げに参画し、日本・アジア・米国企業への投資を担当。その後、幼少期より興味があったスポーツビジネスに携わるべく、2003年、株式会社S-1 スポーツを設立。2004年、楽天株式会社代表の三木谷浩氏に直談判し、株式会社楽天野球団の創業メンバーとなる。楽天イーグルスでは、GM補佐、ファン・エンターテイメント部長、パリーグ共同事業会社設立担当などを歴任し、初年度黒字化成功に貢献する。 2007年、楽天を退社し、株式会社ビズリーチを設立。代表取締役に就任。現在は、年収1000万円以上の転職市場に特化した個人課金型転職サイト「ビズリーチ」、および共同購入型クーポンサイト「LUXA(ルクサ)」を運営する。また、ジュビロ磐田のアドバイザーも務めている。
ライフスタイル
好きな食べ物
焼き肉とラーメン。
焼肉、ラーメン、お好み焼きとか、子どもが好きそうな食べ物が大好きですね(笑)。焼肉なら東京・中目黒の「焼肉JAPAN」、お好み焼きは東京・広尾の「ぼちぼち」によく行きます。お酒はほとんど飲みません。完全に見掛け倒しでめちゃくちゃ弱いです。でも、飲まなくてもテンションが高いので飲みの席は好きです(笑)。
趣味
やっぱりスポーツ。
子どもの頃から、いろんなスポーツをやってきました。今もフットサルやトライアスロンなど、さまざまなスポーツに挑戦しています。時々、仲間と草野球も。先日は仲間の厚意で、ピッチャーをやらせてもらったのですが、その時のキャッチャーが古田敦也さんでした。あれはうれしかったですね。夢のようでした。あとは、漫画。『少年マガジン』は20年間ずっと愛読しています。
行ってみたい場所
アフリカの大草原
父が今、アフリカ市場の仕事をやっているんですよ。旅行好きですので、これまで世界35カ国くらいを旅行してきましたが、アフリカの大草原は完全な未知ゾーン。父からアフリカの土産話を聞くたびに、サファリで大笑いしながら「すげー!」と叫ぶ自分がイメージできるのです。とにかく、一度あのスケール感を生で味わってみたいです
最近感動したこと
「LUXA」の立ち上げ。
さまざまな企業に勤めるサラリーマンや大学生20名が、平日の夜や週末にボランティアで集まり、クーポン共同購入サイト「LUXA(ルクサ)」を8月に立ち上げました。リリース当日の晩に、全員で焼肉を食べながらお祝いをしていたのですが、オープニングパーティーや記者会見の模様がなんとテレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」で放送されたのです。その映像を見ながら、全員が大盛り上がりする姿を見て感動しました。「仕事をしながらでも、やる気があれば何でもできる」と感じさせられた瞬間でした。
人材業界にユーザー視点の風穴を――。
日本初の求職者課金型転職サイトで真っ向勝負!
外資系投資銀行から、楽天イーグルスの創業メンバーを経て起業した、異色の経歴を持つ若きアントレプレナー、南壮一郎氏。彼のモットーは"業界に風穴を開ける!"。その宣言どおり、日本初の求職者課金型転職サイト「ビズリーチ」を立ち上げ、求職者に対して正しい選択肢と可能性の提供ができる仕組みづくりに励んでいる。そのほか、人材業界の仕事内容が正しく求職者に理解されることや人材業界の市場規模の拡大も念頭に新しい価値の創出に取り組む。今年の5月からは、企業の人事部に対しても無料で求職者の情報を公開し、モルガン・スタンレー、ナイキ、マイクロソフト、野村証券をはじめとした、錚々たる企業も参画中だ。「重要なのは、自分の市場価値やキャリアの選択肢と可能性を正しく把握し、自らが進むべき路を主体的に考えること。我々の仕事は、決して転職をお勧めすることではありません。自分の市場価値や選択肢を知ったうえで、今の会社に残ることも素晴らしい判断だと思います。我々が実現したいのは、正しい判断をするための情報提供をすること。なぜならば、人生で一番もったいないことは、本当はやりたいことがあり、実は目の前にチャンスがあるのに、それを知らなかったことだと思いますから」。今回はそんな南氏に、青春時代からこれまでに至る経緯、大切にしている考え方、そしてプライベートまで大いに語っていただいた。
<南 壮一郎をつくったルーツ1>
6歳から13歳まではトロントで。カナダ人として育った少年時代
生まれた場所は大阪でしたが、その後、静岡の磐田市へ引っ越しました。そこで幼稚園に通って、小学校に入る直前に、ヤマハ発動機に勤める父の海外転勤のため、家族でカナダのトロントに引っ越しました。兄弟は、年子の妹と、3つ下の弟。若い頃、海外を放浪して外国人から多くを学んだ父の方針で、日本人が一人も住んでいないトロントの下町で暮らし始めました。当然学校は現地校に通いました。小学校の大半は白人で、6歳の自分はほかの子たちと見かけが違うと感じながらも、この頃は日本人としての意識が薄かったのであまり気にしていませんでした。「英語に苦労しなかったか?」とよく聞かれるのですが、まだ小さかったこともあって、気がついたら話せるようになっていました。小学校時代に一番苦痛だったのは、月曜日から金曜日まで現地校に通いながら、本来お休みの土曜日に、日本人学校へ通わされていたこと。日本人学校では、日本の小学生が1週間かけて習う国語、算数、理科、社会の授業を1日で教わっていました。正直、なぜ周りの友だちが休みの土曜日に、一人だけ学校へ行かなくてはならないかよく分からなく、毎週両親と喧嘩しながら、無理やり日本人学校に通わされていました。後に振り返ると、小学校時代に、人より多く勉強させられたことはその後大きな助けになりました。なぜなら、日本の小学生の授業のレベルはとにかく高いのです。たとえば算数は、日本人学校の授業についていくだけで、現地校では2年飛び級で授業を受けていたぐらいですから。
スポーツは子供の時から大好きでした。とにかく学校が終わると、学校の運動場で泥まみれになってスポーツばかり。カナダらしいといえば、冬になると先生が運動場に大量の水を撒き、体育の授業でアイスホッケーをやっていました。ちなみに、カナダは季節によって所属する部活が違い、自分の場合、秋はクロスカントリー、冬はバレーボール、夏はソフトボールをやりながら、地元のアイスホッケーとサッカーのクラブチームにも所属していました。やるだけでなく、観戦やデータを見るのも大好きで、北米のどのプロスポーツリーグについても関心を持ち、当時は、一日中、ベースボールカードや選手年鑑とか見ていても飽きませんでした。特に大リーグについての知識量なら、相当詳しい部類に入ると思います。
地元にはトロント・ブルージェイズという大リーグのチームがあって、父に連れられよく観戦に出かけました。また、両親が家族の時間をとても大切していたので、冬は毎週末家族でスキー旅行、家の裏側が国立公園になっていたので夏は毎週バーベキューと、のびのびとした少年時代を過ごしました。ちなみに6歳から日本に帰る13歳までの間、家の裏にある国立公園を、父、母、妹、弟と5人で毎朝3キロ走っていました。どちらかといえば、望んだというよりも、父に早朝叩き起こされて、走らされていたに近いですが(笑)。ただ、この毎朝のジョギングで鍛えた体力は、起業した今でも役立っていると感じています。両親はさまざまな面でとても厳しかったですし、よくケンカもしましたが、今ではふたりが理想の夫婦像です。
そうそう、アメリカやカナダでは日本と違って、プロスポーツチームのオーナーがマスメディアに頻繁に登場します。名物オーナーみたいな方もいて、どんなことがきっかけになったか覚えていませんが、とにかく選手以上にオーナーという仕事に憧れました。そんなこともあって、10歳の時からの夢は大リーグの球団オーナーになることでした。今も人生の最大の夢です。別に夢を思い続けることは、人に迷惑をかけることでもないですし、ウソでもないので、子供の頃の夢は、当時から大切にしています
<南 壮一郎をつくったルーツ2>
髪形は丸刈り、揃いのガクランに、靴は白。
軍隊か刑務所か? ここが日本の中学校
中学1年の夏休みに、日本に帰って来ることになりました。幼稚園時代を過ごした磐田市です。完全に日本の小学校をワープしたかたちでの帰国でした。とにかく日本の学校の仕組みを全く理解していなかったので、当初、校則について聞いてびっくりしました。そもそもカナダには、服装や髪型に関する校則はありませんでした。そんな中、校長先生に初めてお会いした時に、髪形は丸刈り、制服は揃いのガクランで、靴は真っ白でなくてはならないと言われ意味がわかりませんでした。さらに、制服の下に着るものは体操服。胸には「南」という名前を書いた布を張らなければならない。ここは、軍隊か刑務所かと……。「どうなっているんだ、この国は」と謎だらけでした。おまけに、転校初日からもう客寄せパンダ状態でしたね。当時は磐田みたいな田舎に帰国子女なんてほとんどいませんでしたから。休み時間になったら、廊下側の窓にみんながズラッと並んで僕を見ている。そうするとテレながら一人の生徒が近づいてきて「おい、おまえ。何か英語しゃべれや」と。何を言えばいいのか全く分からないので「Hello, my name is Jackl」と返答すると、「おお~、すげ~!」と毎回同じ反応が返ってくる。「何なんだ、ここは」状態ですよ(笑)。
またあれは忘れもしない、転校してから1カ月が経った頃の秋祭りの夜。同級生と祭会場の近くに座っていたら、学ランに刺繍が入った見たことがない上級生から「おい、ちょっと顔貸せや」と。そしてススキ風に揺れ、秋本番の野原が広がる空き地に連れて行かれました。まるで漫画に出てくるようワンシーンです。着いた瞬間、「おまえ生意気なんだよ」と言われ、いきなり殴られた。当時まだ、あまり先輩・後輩の関係というものを理解していなかったことや、カナダ時代から喧嘩に巻き込まれることが多かったので、条件反射的に思い切り先輩を殴り返してしまったのです。そしたら、何と草むらから20人くらいの仲間がわらわらと出てきました。「顔じゃなく、腹を狙え」と号令のもと、そこからは逆にボコボコにリンチされました。2、3分くらいだったでしょうか? ひとしきり終わった後に、先輩たちに囲まれながら言われたのは「明日から俺らに会ったら、必ず会釈しろ」。ちなみに、会釈の言葉を知らない自分は「どういう意味ですか?」と聞いたところ、「馬鹿ヤロー!お辞儀だよ、お辞儀!」と言われもう一発蹴られました。ところが僕は、元々あまりめげないタイプなので、翌日会っても平然と「うぃーす」と先輩に会釈しちゃうわけです(笑)。上級生の番長を殴り返したからなのか、めげないところに愛嬌を感じたのかわかりませんが、その後は皆さんにかわいがってもらいました。
ただ、中2になると、家族揃って隣町の浜松に引っ越すことになり、県下一悪くて有名な中学に転校することに……。「またゼロからかよ」と、心が折れそうになりました(苦笑)。ただし、転校してみたら、あまりにも悪い学校だったためか、文部省の指定学校に認定されていて、ものすごく強そうな先生が大量に赴任していたため、荒れていたはずの学校が徹底的に浄化・鎮圧されていたので平和そのものでした。ちなみに、僕の担任は身長185センチ、砲丸投げの元学生チャンピオンで、常日頃からサングラスをしていました(笑)。高校は地元の県立浜松北高へ。中学から高校まで、ずっとサッカー部に所属していました。カナダでサッカークラブに入っていたとはいえ、さすがサッカー王国・静岡。レベルは高かったですね。中学の先輩にJリーガーになった方もいましたし、高校時代の後輩は全日本に選ばれていました。何しろ負けず嫌いですから、レギュラーを取る以外考えられず、必死でした。中学はずっと補欠だったのですが、高校時代は、朝から晩までサッカー漬けで、思い出はほとんどサッカーのみです(笑)。"スポーツに国境なし"とよくいわれますが、そのとおりだと思いました。中学のサッカー部の先輩たちは、陰湿ないじめから守ってくれましたし、ストイックに打ち込んだことで、非行の道に走ることもなかった。高校時代は最終的にはキャプテンを任され、静岡県西部地区選抜にも選ばれました。ただプロ選手になろうとは一度も思ったことはなく、それよりも、当時もプロスポーツチームのオーナーになることしか考えていませんでした。
<アメリカの大学へ進学>
自分が選んだ路だからこそ突き進む。世界のどこにいっても頑張れば何とかなる!
僕がいた浜松北高は進学校だったため、自分も最初は周囲と同じように普通に東大を目指していました。あれは高2の終わり頃のこと、本屋で立ち読みしていたら、たまたま雑誌の表紙に世界の大学ランキングというタイトルが書いてあるのが目に入ったのです。中身を開いてみたら、びっくり。なんと東大が40位くらい。衝撃でした。まだまだ自分が知らない世界があるんだ。負けず嫌いの僕にとっては、日本の大学という枠に囚われず、世界を目指したほうが、挑戦する甲斐があると直感的に感じ、すぐに父に「アメリカの大学へ進学したい」と相談しました。そうしたら、父は迷わず「自分のことは自分で決めればいい」と言ってくれました。翌日、高校の担任にアメリカへ行くことを告げると、先生は大反対。そんなの「前例がない」の一点張り。とにかく日本の大学に行ってから、アメリカへ留学しろと。そこからは、毎日のように、違う教科を担当する先生から「そんな夢みたいなこと言ってないで、受験勉強しろ」と言われ続けました。またもうひとつの問題は、今のようにネットがあったわけではないのと、田舎だったので、誰に聞いてもアメリカの大学の受験方法について全く情報が見つからない。そんな時、カナダの日本人学校で一緒だったら友人のお父様から、新宿の紀伊国屋書店の洋書コーナーにアメリカの大学関連書があるという情報を入手しました。浜松の田舎で育った僕にとって、新宿はとても遠い未知の街です。けれど、そんなことで自分が決めたことを簡単にあきらめたくはない。すぐさま浜松から新宿まで本を買いに行って、アメリカの大学受験の基本的な仕組みを把握することができました。同時に、アメリカ人の高校生が、高校3年生になる前の夏休みに大学の調査旅行を行うことが多いということが本に書いてあったので、高3の夏休みに、単身で渡米し、UCバークレーやスタンフォード大学の現地キャンパスツアーに参加。キャンパスツアーは、アメリカの高校生でさえ、親と一緒に参加するのが通例です。しかし父親は「忙しいから一人で行け」と(笑)。18歳で単身アメリカを巡るというのは、なかなか刺激的な体験でした。同時に、主体的に動いたからこそ「アメリカの大学に行きたい」という思いがより一層強くなりました。ただ、とにかく英語力がカナダから帰国した時点で完全に止まってしまっていたので、中学1年生レベルの英語力を徹底的な勉強で補っていきました。また、秋に入ってからは毎週土曜日に「青春18切符」を使って、浜松から往復10時間もかけて、東京・渋谷にある海外大学の受験予備校に通いました
高校の先生たちからは、「考え直せ」「東大に行ってから海外留学をすればいいじゃないか」と、かなり説得されましたが、僕の意思は一度も変わりませんでした。結局、どの先生も協力してくれないので、アメリカに送る成績表は親のワープロの「一太郎」というソフトで作成し、非協力的な担任を無視して、サッカー部の顧問から推薦文を書いてもらって、自分で英訳して使いました。志望校については、当時ロンドン在住だったカナダ時代の友人もアメリカの大学を受けるというので、国際電話で彼が受ける大学を聞き出し、彼と全く同じ大学を受験しました。結果的に、いくつかの大学から入学許可が届いた中で、街や雰囲気が気に入ったタフツ大学への進学を決めました。漠然とボストンにある大学だとハーバード大に編入できるかもしれないという理由も影響しました
タフツ大学に進学が決まり、アメリカでの生活がはじまるのですが、これまた父親の方針で、毎年1年間の授業料と生活費を年初に渡されて、これで自由にやれと言われました。そこで良い事を思いついたと感じた僕は、前期分の授業料をまず収め、残ったお金をなぜか株式で運用することにしました。今考えるとかなり恐ろしいのですが、若い時はリスクを全く考えていませんでした。大学では、とにかくアジア人だけと群れないことを心がけ、勉強やスポーツなど、目の前にあることのすべてに全力投球で挑みました。気質や価値観が近いアジア人と一緒にいると確かに楽なのですが、せっかくアメリカにいるのだから、アメリカに順応して、白人社会のど真ん中でどこまで自分が通用するか試してみたかったのです。アメリカで認められるには、とにかく学校の成績は当然、スポーツもでき、社交性も求められます。そんなこともあって、1年生からサッカー部に入部し、必死に練習に励みました。サッカー漬けの高校時代を送っていたことも幸いして、2年からはレギュラーに抜擢され、シーズン当初から得点を重ねていきました。その活躍が「タフツ・デイリー」という大学の日刊新聞の1面を飾り、そのおかげで、少しずつですが白人の輪にも入れてもらえるようになりました。その後、生徒会に立候補し、選挙を経て、評議委員に当選。入学当初は、周囲の会話のスピードにも内容にもついていけなく、毎日、学食の端っこが指定席だった僕が、努力によって、アメリカ人の仲間たちと、学食のど真ん中の特等席に堂々と座れるようになりました。結果的には、大好きで小さい頃から練習していたサッカーにまた助けられたと思っています
<モルガン・スタンレーへ>
ビジネスプロフェッショナルとしての土台は、
モルガン・スタンレーの修業で培った
実は大学3年だった1997年、僕は日本の上智大学へ1年間だけ交換留学していたんですよ。普通はあり得ないですし、さすが両親も驚いていましたが(笑)。改めて外から日本を見る機会をもらえたということで、日本が素晴らしい国ということを再認識できた。しかし、明らかにマイナスな部分もある。卒業したらアメリカで仕事をしたいと考えていたからこそ、大学在学中に、再度日本に住み、日本人としての自分のアイデンティティを再確認しておきたかった。もちろん県立高校を卒業した自分を受け入れてくれる学校は表向きにはなかった。自らの理由を手紙にして、いくつかの大学へ再打診してみたんです。そうしたら、上智大学が僕の「逆」留学を受け入れてくれました。そんな思いを持ちながら迎えた1998年2月。たまたま長野オリンピックが開催されており、大好きなスポーツの祭典であるオリンピックに関わった仕事をどうしてもしたいと、いろんな人脈をたどり、運よく通訳の仕事ができることになったんです。昔から憧れのヒーローだったカナダ人のアイスホッケー選手にインタビューしたり、目の前では日の丸飛行隊の原田雅彦さんが団体で金メダルを獲って号泣していたり。自分は今、すごい場所にいるんだと、強烈に感じました。この時に、いつか必ずスポーツビジネスに携わろうと、心に決めました。
時は同じ頃、スポーツマーケティングビジネスの第一人者、ジャック坂崎さんが書いた『フェア』という本を読んで感動しました。これもまた、子供の頃からお世話になった方が、ジャックさんと仲良かったこともあり、就職相談というかたちでお会いできることになりました。そして、「自分もスポーツビジネスを手がけたい」と熱く語ったら、「スポーツ業界では、ビジネスマンとしての土台はつくれない。まずは、ちゃんとした業界で3年修行してこい」と一蹴されました。そういうことかと、アメリカの同級生に色々とヒアリングしてみると、多くの学生が、「モルガン・スタンレーかゴールドマン・サックスに行きたい」と言います。自分も数量経済学と国際学を専攻し、数字が得意でしたから、ウォールストリートで働くのも面白そうだと。そもそも日本に帰国するつもりはなく、当然のようにアメリカで働くと思っていました。ところが、腕試しのつもりで参加した日本人留学生向けの就職フェアで、モルガン・スタンレーからオファーをいただき、迷った挙句に直感で東京支社の投資銀行部で働くことを決めました。
結果的には、その直感は間違っていませんでした。ビジネスパーソンとしての自分の土台ができたのは、すべてモルガン・スタンレーで修業させてもらったからこそだと思います。最高で週138時間も働き、体力的にも内容的にも仕事はとてもハードでしたが、世界中の経営者や企業とお仕事ができ、数々の重要案件に携わることができました。そして、何よりも一緒に働いた先輩、上司の方々のみならず、同期の仲間は、とにかくみんな優秀。これが世界最高峰の働き方だ、一流になるにはこのくらいの仕事ができないといけないんだと、自分が目指すべき高い基準値が自然と確立されました。ただ、つらいと感じたことは一度もありません。なぜかというと物事には必ず終わりがあります。終わって結果が出た時に、最高の満足を得るためには、今この瞬間の努力を重ねるしかない。満足の大きさに努力は比例していると信じることも学びました。今から思い返してみると、うまくいったことじゃなくて、上司や仲間と一緒に苦しんだことばかりが思い浮かびますが(笑)。まあ、いくら仕事をしても命まで取られることはないと、必死で仕事に取り組んでいました。
●次週、「楽天野球団の創業メンバーを経て、人材業界の改革に挑む!」の後編へ続く→
外資系投資銀行、楽天野球団創業メンバーを経て
起業した異色の経歴を持つアントレプレナー
<やっぱりスポーツビジネスしかない>
個人でスポーツビジネスに挑むも目標設定が甘く、半年で貯金が底を突く
モルガン・スタンレーで働き始めて2年目の頃、当時のクライアントから声がかかりました。香港・PCCWグループが日本市場に進出する際に、日本の上場企業を買収するお手伝いをしたのですが、買収後に、投資担当者から約300億円の新しい資金を会社に投入するので、一緒に投資事業をやらないかというお誘いを受けました。日本、アジア、アメリカなどの世界中の企業を買収していく計画も知らされました。まだキャリアの先は長いので、いったんモルスタの外に出て、投資をお手伝いする側ではなく、実際投資する側の仕事をするのもいいかと思い、悩みながらもその話にのりました。結果論からするとさまざまな失敗もありましたが、世界中を一人で飛び回り、さまざまな会社やビジネスモデルを見ることができたことは得難い経験となりました。ただ、ITバブルが弾けて、仕事が少し暇になって、さて、これからどうしようかと考えたのが2002年頃。日韓ワールドカップが開催された年でした。
さまざまな縁のおかげで、手元に日本対ロシア戦のチケットが30枚ほどありました。そこで仲間を誘って観戦に行きました。日本が1対0でロシアを撃破し、ワールドカップで初勝利した試合です。スタジアムを真っ青に染めた7万人のサポーターが、全員、誰かれかまわず抱き合って号泣。僕も勝利の瞬間、体に電気が走って、鳥肌が立つほど大きな感動を覚えました。そして、「こんな感動を今の仕事で味わうことができるのか?」と自問自答した。
それまで何不自由なく外資系金融マンとして生活をしながら、何かが足りなかった。2002年のワールドカップの感動を現場で味わってしまったことで、いてもたってもいられなくなりました。ワールドカップが終わると同時に、大学時代に相談に乗ってもらったジャック坂崎さんに再度連絡。「坂崎さんに言われたように、3年間金融業界で死にもの狂いで頑張ってきました。スポーツビジネスの世界で働きたいので、どこかよい会社を紹介していただけないでしょうか?」そうしたら、「スポーツ業界をなめているんじゃないか? 本当に業界に入りたいなら、自分の力で扉をこじ開けてみろ」と……。まあ、当時は全く理解できなかったのですが、彼なりの愛の鞭だったんでしょうね。
その後、有給休暇を使ってアメリカに飛んで、大リーグのゼネラルマネージャー(GM)や、敏腕スポーツエージェントに会いに出かけました。とにかくアポなしの夜討ち朝駆け、待ち伏せて会うという戦法でしたが、ニューヨーク・メッツのGMやイチロー選手のエージェントなど、自分が憧れていた職業に就いている方々にお会いできました。ただ、残念なことに、仕事というかたちでの結果は実りませんでした。結果的には、これ以上サラリーマンを続けながらスポーツビジネスに挑むのは難しいと判断し、2003年にPCCWを退職。スポーツビジネスの世界へ飛び込むための個人会社を立ち上げることにしました。
しかし勢いで会社をつくったのはいいのですが、スポーツの仕事を得る手段など全くわかりません。まずはできることから片っ端にやろうと、フットサル場の管理人やテニスの国際大会の通訳、格闘家をマネジメントする会社のお手伝いと、とにかく目の前に転んできた業務を何でもやりました。ただ、時間が経つだけで、何も進展はありません。やはり、目標設定が甘すぎたんですね。半年くらいで貯金が底を突き始めました。そんな時、前職で大変お世話になった喜吉憲さんがカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)の常務として転職されていたことを聞きつけ、何かお手伝いすることはないかと相談に伺ったのです。タイミングが良かったのか、私が苦労しているのを見抜いてなのか「企業買収を手伝ってくれ」と声をかけてくれたのです。ご縁というものはどこでつながるか分からないもので、だからこそ、一つひとつの仕事を全力でやり遂げることが重要だと感じた瞬間です。社会人になってからずっと、週100時間を超えるハードワークを続けてきましたが、見ている人はきちんと見てくれているものです。CCCでは、喜吉さんからの依頼はすべてこなすように心がけ、これまで培ってきた経験をフルに生かして仕事をしました。買収案件のお手伝いということもあって、その縁で、CCCの創業者である増田宗昭社長ともお仕事を何度かさせていただく機会にも恵まれました。そして、2003年末、増田社長がエンジェルインベスターとして関わりのあった、楽天の三木谷浩史社長を紹介していただいたのです。これが三木谷社長との初めて出会いでした。
三木谷社長からその時にかけていただいた言葉は今も忘れません。「世間は私が日本興業銀行を辞め、すぐに楽天を創業して成功したと見ているが、それはとんでもない誤解だ。本当に、色々な苦労があった。そして、その時に大変お世話になったのが、増田社長だ。時代が巡って、今度は君のような若い金融マンが安定した生活を捨て、新しいことに挑戦しようとしている。今度は私が君を助けてあげる番だ」。この縁を通じて、楽天からも企業買収のコンサルティング契約をいただけました。結局、昼はスポーツ関連の「丁稚奉公」のような仕事をこなし、夜は企業買収の資料づくりや金融マン時代の友人たちが振ってくれた財務資料の翻訳をする日々を1年半続けました。ただ、スポーツビジネスをやりたくて会社を辞めたはずなのに、結局生活費は金融の仕事で稼いでいる。僕は正直焦っていました。
ところが、チャンスは動いている人の元に訪れるものです。2004年6月に、突如として、大阪近鉄バファローズとオリックス・ブルーウェーブの合併に端を発するプロ野球再編問題が勃発。9月に入り、そこに楽天が名乗りを上げ、ライブドアとの参入レースに参戦することになりました。私はそのニュースを見た瞬間、すぐに楽天の三木谷社長に連絡してアポイントの時間をいただいた。与えられた時間はたった20分。その20分にこれまでのすべての思いを込めてプレゼン。約束の時間が終わった後、三木谷社長の返事は、「それでは、明日から来てください。」でした。
<楽天野球団の創業メンバーに>
暗中模索で取り組んだ、大量かつ難易度の高い仕事。
すべては鳥肌が立つあの瞬間を味わうために……
2004年9月、株式会社楽天野球団の創業メンバーとしての仕事が始まりました。最初のオフィスは、楽天本社内の10畳程度の会議室でした。当時の僕はまだ28歳。とにかく、開幕まで半年の間に球団をつくらなくてはならないのに、メンバーは10名程度しかいない。それ故に、僕のような若造の手元にも、選手の契約書作成、チームのスケジュール調整、キャンプ地の選定、2軍の立ち上げ、スタジアム事業の立ち上げなど、同時に7、8個のプロジェクトが任される。会社側にとってもバクチ的な要素もあったと思います。とにかく必死で目の前の仕事に取り組みましたが、さすがにパンクしそうでした。一度だけ、三木谷さんに弱音を吐いたことがあります。すると三木谷さんは、「仕事は選ぶものじゃない。与えられるものだ。ただし、一つだけ忘れないでもらいたいことがある。仕事はできる人間にしか集まらないので、集まるうちは歯を食いしばって頑張りなさい。」という一言でした。それから2007年までの3年間、さまざまな苦労や困難に直面しましたが、その度に、その言葉を思い出し、弱音を一切吐くのをやめました。そのおかげもあり、自分なりの限界はつくらず、新しい仕事を通じていろんな提案をし、実行し、何とか満足のいく結果を残せたと思っています。
ちなみに、楽天時代の思い出深い出来事は星の数ほどありますが、ここでは2つだけ紹介しておきます。あれは1年目のシーズンが終わった頃。営業先のオフィスを出て、天気が良かったので、駅に向かって歩いていた時です。ふと歩道を見ると、保育士に連れられた20人ほどの幼稚園児が、公園にでも行くのかよちよち歩いていました。その行列をよく見ると、20人のうち17人がなんと楽天の赤い帽子をかぶっている。そうです、僕たちがゼロからつくったロゴをまとった帽子をかぶっているのです。それまで、スタジアムに閉じこもって仕事をしていたことが多かったので、街の変化にあまり気付いていなかったのです。楽天が仙台市民に溶け込み始めていることを肌で感じることができ、涙が出るくらいうれしかった。
もうひとつは、2年目のシーズンの最終試合でのこと。雨の振り替え試合だったこともあって、東京での予定と調整がつかず、三木谷社長は観戦にいらっしゃいませんでした。実はすでに3年目に楽天を離れることは球団の上層部には伝えてあったので、僕にとって楽天での最後のシーズン最終試合。そして、試合前に楽天の島田亨球団社長から伝言を受けとったのですが、なんと三木谷社長から「最後だから俺のオーナーボックスを使っていいぞ」という伝言でした。スタジアム全体を見渡すことができるオーナー部屋のバルコニーに一人で座り、試合を最初から最後まで観させてもらったのですが、そこからスタジアム全体を見渡すと、目の前に広がる景色は、すべて自分たちでつくってきたものでした。そのうえ、球場全体が楽天ファンで埋まって真っ赤に燃えている。「あっ、まさにこれを求めていたのかも」と思ったその瞬間、体中に鳥肌が立ち、大粒の涙がこぼれ出しました。俺はこのために仕事をしてきたんだなあと。10歳の時からの夢である球団オーナーの夢には、まだ全然辿り着いていない。ただ、夢が一生叶わなかったとしても、あの瞬間、自分は少しだけですが、夢の世界を垣間見ることができたのです。
そして、人生の中であと何回、仕事仲間と一緒にこれほどの感動の涙を流せるんだろうと考えました。僕にとって、仕事は人生で最高のエンターテインメントなんです。仕事を通じて非日常の感動をどうつくるかが問題。大学を出て、9年間、毎週確実に100時間以上、仕事をしてきました。「フェリスはある朝突然に」という大好きな映画に、「Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.」というセリフがあります。このセリフのとおり、ここらで少し立ち止まり、今後の人生、何をすべきかじっくり考えようと思いました。そもそも、僕は絶対に起業したいわけではないんです。直感で面白いと思えること、新しい価値を創出し、世の中に残せることなら、会社の形態も関係ないし、ポジションなんてどうでもいい。だから面白いことを見つけるために、いろんな人に会いに行き、世の仕事を探すために、転職サイトまでも初めて使ってみた。ただ、この行動が、後にビズリーチを立ち上げる、理由なったのです。
<未来へ~ビズリーチが目指すもの>
転職を斡旋するのではなく、ビジネスプロフェッショナルに
正しい選択肢と可能性を提供したい
自分自身が求職者として仕事を探してみて、世に定着した転職サイトは確かに便利だと思いましたが、僕自身の希望する仕事が全く見つからない。第二新卒クラスの情報はいくらでもあるのですが、中間管理職や専門性の高いビジネスプロフェッショナル向けの情報は実に見つけにくい。ならばと、20人以上のヘッドハンターに会って、仕事を紹介してもらいましたが、全員が全く違う手持ちの求人を出してくる。レストランでいえば、一人ひとりのウエイターが別々のお勧めメニューだけを出してくるようなもの。そうではなく、まずはその店のアラカルトも全部見てからオーダーしたいじゃないですか。新卒向けには、リクナビなど、レストランの全メニューが見られる素晴らしい仕組み(アラカルトのメニュー)があります。でも、30代以上のビジネスプロフェッショナルが有効活用できるような転職サイトが全く存在しない。だったら、自分が使いやすく、会社も使いたくなるようなプラットフォームをつくってみたいと。
僕は社会人になってから、常に自分が「正しい」と思うことを追い求めてビジネスに取り組んできました。プロ野球ビジネスも、楽天が出てくる以前は、多くの球団が観客動員数を推定人数で公表しており、実は発表される数字と実数には1万人もの誤差があることがありました。他球団からは当初強い反発はありましたが、楽天が実数で観客動員数を出す意向を示すと、他球団も実数を公表し始めました。人材ビジネスも同じ。誰がお客様であるかを明確にして、お客様にとってベストなビジネスモデルをつくることこそ、業界全体の改善と活性化につながるはずです。日本初の求職者課金型転職サイト「ビズリーチ」のビジネスモデルは、ほかの転職サイトとは異なり、求職者から利用料を徴収し、採用企業やヘッドハンターの利用料金は無料です。また、ボリュームゾーンである年収400万円~700万円の求人を抱えている既存の転職サイトとの差別化を図り、求人情報は年収1000万円以上のものに限定し、利用できる求職者も前職の年収が750万円以上の方に限定しました。よく聞かれるのが、なぜ求職者から利用料を徴収するかという理由。僕にとっては、極めて単純なことなのですが、お金を払ってもらってこそお客様だと思うからです。既存の人材ビジネスのほとんどは、企業からお金をもらって運営しているサービスがほとんど。つまり、求職者の目を見て「あなたは我々にとって真のお客様です」と堂々と言えるような人材ビジネスがあってもよいと思ったからです。その思いを追求してできたのがビズリーチでした。
2009年4月にカットオーバーしてから約1年半、「ビズリーチ」は着実に進化を続けています。今では会員数約4万人、ヘッドハンター約500人が登録。今年の5月からは、企業の人事部にも広く利用していただけるようサービスを公開し、モルガン・スタンレー、ナイキ、マイクロソフト、野村証券等、錚々たる企業に利用いただいています。もちろん、国内だけにとどまらず、日本のビジネス・プロフェッショナルが、アジアなど、世界中での活躍の機会を見逃さないように、このビジネスを海外にも展開していきたいと思っています。大学時代から常に感じているのですが、多くの日本人は、世界中のどこにいっても活躍できるくらいの力は持っています。日本で働いている皆さんに、海外にも面白い仕事があることを知ってもらいたい。そして自分の可能性を知り、やりたいと感じたなら、積極的に手を伸ばしてほしい。人生において一番もったいないこと。それは本当はやりたいことがあるのに、それを知らなかったことだと思いますから。
<これから起業を目指す人たちへのメッセージ>
起業する場合に一番重要なのは「大義名分」。
不満や不便の解決が最大のポイント
僕の働き方って、とてもシンプルなんですよ。そもそも会社って、ひとりの人が中心となって立ち上げるケースも多いと思うのですが、僕の場合、役割分担をきっちり分けて、能力が異なる仲間を集めながら事業を作っていく方が好きです。僕が好きなアニメで「サイボーグ009」というものがあるのですが、多種多様な国籍の男女が、それぞれ特殊能力を持って、力を合わせながら悪と戦っていく。新規事業を立ち上げるうえで、自分が理想とするチームは、それぞれ違った特殊能力をもった仲間が集い、共通の目的を目指して頑張ること。また同じ気の合ったチームで、いろんな業種で、何回も何回も、新しい価値を世に送り出したいとも思っています。
また起業する際に一番重要なのは、大義名分じゃないのかなと。自分が不満や不便に思うことを解決する、これ以上、これ以下のポイントはないように思えます。同時に、その問題の解決策をつくり出すことで、業界や社会全体にどのような影響を与えるか、そして成功した時に世の中にどんなプラスをもたらすことができるのか。また最近よく起業の相談を受けますが、皆さん、起業を難しく考えすぎているように感じます。実は、ビズリーチは元々10名のボランティアが中心となって始めた事業です。その10名のボランティアは、全員、さまざまな企業に勤務するサラリーマンです。サイトの準備から始まり、リリースしてからも平日の夜や週末を利用して、ビズリーチの成長に貢献してくれた大事な仲間たちです。ちなみに、サイトの準備を始めてから1年間くらいはそのような体制で、なるべくコストをかけずに頑張っていたのですが、ベンチャーキャピタルから資金調達することができたので、すぐに彼らを一人ひとり正社員として迎え入れていきました。起業をしたいけれども、現在のお仕事を辞めるリスクが高すぎると思っている方は、ぜひ平日の夜や週末の時間の使い方を一度書き出してみて、逆にその時間をすべて利用したプロジェクトチームをつくってみることをお勧めします。そんな感じで、まずはやりたいことをボランティアとして始めてみて、うまくいきそうなら勝負すればいいんです。
いずれにせよ、人生は一度きりです。仕事については、周囲の声を気にせず、自分自身が信じる価値観に従って進めばよいと思います。仕事を頑張りたい人は頑張ればいいし、仕事よりもプライベートを充実させたい人は、そのような生活を実現できるように努力すればいい。重要なのは、主体的に自分がやりたいようにやることです。その気持ちさえ忘れなければ、どんなことも不可能ではないですし、きっと社会に貢献できるような仕事ができるようになると思います。
<了>
取材・文:菊池徳行(アメイジングニッポン)
撮影:内海明啓